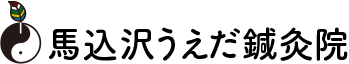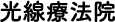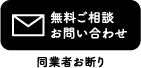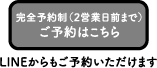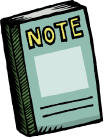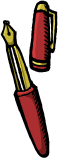五行論2

上田
馬込沢うえだ鍼灸院院長
鍼灸でみんなを幸せにしたいと
日々精進

roo
健康に興味のあるネコ
出身地:千葉
好きな食べ物:肉

roo
五行論のお話しを伺いました

上田
はい

roo
自然界の、木、火、土、金、水がそれぞれ影響し合って、バランスをとっている

上田
そう

roo
このバランスが崩れると不都合が生じる

上田
はい

roo
人間の体であれば病気になる

上田
そう

roo
バランスのとり方には、相生と相克があって、相生は、別のものや相手の力を生む関係、相克は相手の力を抑制する関係のこと

上田
そう。いいものは生まれた(増えた)ほうがいいし、悪いものは減ったほうがいいね

roo
はい。いい気はしっかりと巡ったほうがいいし、悪い気は巡らないほうがいいですね

上田
そうだね。いい気であっても、巡らないと悪い気になるよ

roo
といいますと

上田
例えば、肝には「疏泄」という働きがあるんだけど、疏泄とは「淀みなく」とか「スムーズ」という意味で、この疏泄の働きがうまくいっていれば、他の4臓(心、脾、肺、腎)の調子もいい

roo
はい

上田
しかし、疏泄の働きがうまくいかなくなると、気は滞って「気滞」となる。肝鬱気滞ともいうね

roo
肝鬱気滞

上田
その状態が続くと、こんどは肝鬱化火となって、体にとってありがたくない火が生まれてしまうんだ

roo
肝鬱化火、ありがたくない火

上田
すると、そのありがたくない火は、肝の子である心に悪影響を与えるようになる。これが肝心火旺

roo
肝心火旺になると、眠れなくなったりするんですよね

上田
そう。眠たくでしょうがないのも困るけど、眠れないのも困るね

roo
困ります

上田
この状況(肝が暴走した状況)が脾に影響した場合、食欲や消化器系統に異常をきたすよ

roo
神経性胃炎、過敏性腸症候群なんかですね

上田
そう。本来、木の特性をもつ肝は、土の特性をもつ脾の働きを適度に抑制している

roo
木克土の関係ですね

上田
木克土は正常な状態だね。しかし、肝が脾の働きを抑制しすぎると「木乗土」という病的な状態になってしまうんだ

roo
木克土は正常、木乗土は異常

上田
中でも、もともと脾が弱くて、肝の力が特別強いわけでもないのに、少しのストレスで脾の調子が悪くなるものを「土虚木乗」というよ

roo
肝が強過ぎるのが木乗土、脾が弱いのが土虚木乗

上田
そう。どちらも木克土が過ぎた状態だね。逆に、脾が強すぎて、肝が脾を抑えられない状態を「土侮木」というよ

roo
土侮木。下克上ですね

上田
ある意味、食欲過多は「土侮木」と捉えることができるね。腎水が心火を抑えられない不眠なんかもそう

roo
なるほど

上田
食べることは、とても大切なことでしょ

roo
とても大切です

上田
食べ過ぎもよくないし、食べなさ過ぎもよくない。何を食べるか、ということもとても大切だね

roo
何を食べるか、ということもとても大切です

上田
ちゃんとしたものを、適量食べていれば病気になりにくい。なっても治りやすい

roo
はい

上田
食事と同じく、運動と睡眠もとても大切だね

roo
はい。食事と同じく、運動と睡眠もとても大切ですね。健康のためには、食生活がどんなによくても、運動不足、睡眠不足では不十分です

上田
そのとおり。適度に運動すれば呼吸も調って、肝を始め、他の臓腑もよくなる

roo
正しい肺の働きで、肝の暴走を止めるんでしたよね。これが「金克木」。逆に肺が肝を抑えられないのが下克上の「木侮金」。そういった意味でも運動は大切ですね

上田
そうだね。それからしっかりと睡眠がとれれば腎が充実する。すると腎陰が養われて、肝陰も、心陰も潤う

roo
すべてつがっているんですね

上田
そう。だから全体をみることが大切なんだ

roo
はい

上田
根本療法のためには全体をみることが必要だし、

roo
部分的にしか見なかったら対症療法になってしまう

上田
対症療法も大切だけどね

roo
とりあえず症状を軽くしつつ、全体もしくは根本をよくしていくのが大切ということですね

上田
そういうことです
五行(木、火、土、金、水)のそれぞれの関係で、正常な状態が相生、相克。
異常な状態が、相乗、相侮(下克上)。
親は子を叱らなくてはならないときがあります。
しかし、子ののびやかさが失われてしまうほど叱ってはいけません。
もしくは、そのような叱り方をしてはいけません。